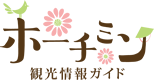異国での食体験は、文化の違いを最も色濃く感じられる瞬間の一つです。特に、両国に存在するのに、一方では「普通」に食べ、もう一方では「食べない」あるいは「食べ方が大きく異なる」食材や料理は、驚きと発見に満ちています。
ベトナムでの日常で見かけるけれど、日本ではめったに食卓に上らないもの、またその逆のパターンを見ていきましょう。
ベトナムでは普通だけど、日本ではなかなか食べないもの
ベトナムでは栄養源として、あるいはローカルフードとして親しまれているのに、日本では食材としての流通が少なかったり、食習慣になかったりするものが多数あります。
1.ニワトリの「全部位」とその他の生き物たち
ベトナムの食卓では、鶏肉を余すところなく利用する文化が根付いています。
ニワトリの全部位(内臓・足など)
日本では鶏肉と言えば、胸肉、もも肉がメインですが、ベトナムでは鶏の足やレバー、キンカン(未成熟な卵)といった内臓も広く食べられます。日本では専門店や中華料理店などで見かける程度で、日常的な食材ではありません。

カエル・タニシ・ザリガニ
特にカエルの肉は、淡白で鶏肉のような味わいから、ベトナムのローカルレストランではポピュラーな食材です。また、タニシやザリガニも、ビールのおつまみや炒め物として楽しまれます。日本ではカエルやタニシを日常的に食べる習慣はほとんどありません。

豚の血 加熱した豚の血を固めたもの(Tiết Luộc)は、ベトナムの麺料理などと一緒に食べられる料理です。日本ではあまり見られませんし、衛生面から見ても敬遠されがちです。食感は固めの豆腐みたいでレバーのような味がします。

2.生卵はNG? 卵の調理法と「生の文化」
ベトナムと日本では、同じ食材でも「生で食べるか、火を通すか」の文化が大きく異なります。
生卵
日本で愛される卵かけご飯のように、生卵を食べる習慣はベトナムにはありません。衛生管理の違いや、生食への抵抗感から、ベトナムでは卵はたっぷり油で揚げる、もしくは固くゆでるのが一般的です。スーパーなどで売っている卵は基本的に生食不可です。生食したい場合は生食可と明記されている卵を買う必要があります。

パクチー
ベトナム料理に欠かせないハーブ(Rau thơm)。日本ではまだ苦手な人も多いパクチー(ベトナム語でRau Mùi)ですが、ベトナムではフォーなどの麺類に山盛りの生ハーブを添えて、その香りとシャキシャキ感を楽しみます。日本では薬味やアクセントですが、ベトナムでは野菜・副菜の主役級です。

日本では普通だけど、ベトナムではあまり食べないもの
逆に、日本では一般的なのに、ベトナムでは食習慣になじまないものもあります。これは、食材の好みに加え、調理法や食感の好みが大きく影響しています。
1.生の食文化と調味料の違い
日本独特の「生の文化」と、ベトナムではあまり使われない調味料に注目します。
ワサビ
ベトナムでもお寿司は人気がありますが、ワサビの「鼻に抜ける辛さ」は、ベトナムの方にはあまり受け入れられないことがあります。ベトナムの辛味は主に唐辛子のチリソースであり、ワサビとは種類が異なります。
刺身・寿司(生魚)
ベトナムでも魚介類はよく食べられますが、生の魚介類を食べる習慣は日本ほど浸透していません。寿司も、アボカドやカニカマを使った加熱・創作寿司が人気で、醤油ではなくマヨネーズやチリソースをつけて食べることが多いです。ここ数年でかなり普及しましたが、日本料理という枠を超えて一般的に食べられているわけではありません。

味噌汁(味噌の風味)
日本で欠かせない味噌汁や味噌の風味は、魚醤(ヌクマム)を基本とするベトナムの食文化とは異なります。ベトナムでは野菜を使ったスープが一般的です。
2.食感が苦手?特定の加工食品
羊羹
ベトナム人も甘いものは好きですが、日本の羊羹の「寒天で固めた食感」と「独特の濃厚な甘さ」が苦手な方が多いようです。ベトナムでは、よりさっぱりした緑豆を使った餡子スイーツが好まれます。

まとめ:食の異文化交流は「食べ方」から
日本とベトナムの食文化の違いは、単に「何があるか」ではなく、「どう調理し、どう食べるか」という点に深く根ざしています。
ベトナム人が日本の生卵やワサビに驚くように、日本人がベトナムのカエル料理やニワトリの足に戸惑うのは、それぞれの国で培われた安全基準や美意識、そして食の歴史が異なるからに他なりません。
異国の食卓を囲むとき、これらの「食べないもの」を知っておくことは、より深い文化理解への第一歩となるでしょう。