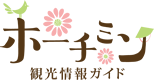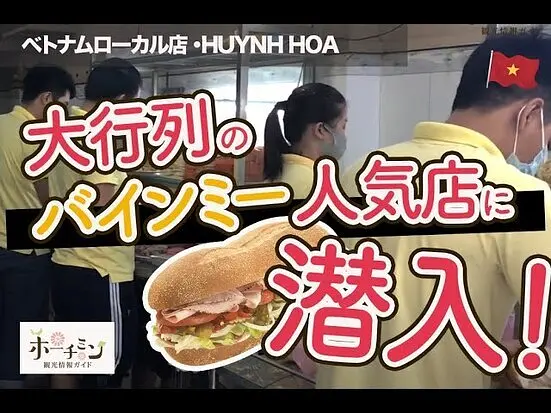目次
ベトナムに住んでいると、いたるところで見かける単語があります。
それが「bánh(バイン)」です。
bánh mì(バインミー)、bánh xèo(バインセオ)、bánh bao(バインバオ)……。
食べ物の多くに “bánh” がついており、ホーチミンで生活しているといつの間にか耳に馴染む単語になります。
しかし、bánh とは何なのか?
パンのようで、餅のようで、ケーキのようでもある。
何となくイメージはできるのに、説明しようとすると意外と難しい――そんな言葉です。
1.bánh を使った代表的な料理たち

日常でよく見かける “bánh” つきの食べ物を挙げると、たしかに種類がとても多いことに気づきます。
bánh mì(ご存知。バインミー)
bánh bao(肉まん/豚まん)
bánh xèo(旅行者に人気のベトナム風お好み焼き)
bánh cuốn(私の一押しベトナム料理)
bánh gạo(おせんべいやおかきなどの米菓子)
ここまで違う料理が一つの言葉でくくられているのは不思議で、
「bánh とは何か?」という問いの奥深さを感じます。
2.発音のちがい――ハノイでは「バィン↑」、ホーチミンでは「バン↑」
bánh は北部と南部で発音が少し違います。
ハノイでは「バィン↑」、ホーチミンでは「バン↑」のように聞こえます。
在住していると、このニュアンスの違いが地域性の違いと重なって聞こえることもあり、興味深いポイントです。

3.bánh 単体では意味がとらえにくい
bánh を辞書的に説明すると、
「粉ものの食べ物」というような非常に広い意味になるようです。
しかし、実際にはパン・餅・クレープ・ケーキなど日本語なら別々に分類しそうな食べ物まで
ひとまとめに “bánh” になる場面が多くあります。
そう考えると、bánh は単語というより “感覚的なカテゴリ” に近いのかもしれません。
4.bánh の多様性と、「とりあえず bánh をつける」感覚
ベトナムでは、bánh を使った単語が本当に多いです。
bánh cuốn、bánh bèo、bánh chưng、bánh tét……。
さらに面白いのは、外国の食べ物にまで “bánh” がつけられることです。
bánh mochi(餅)
bánh pizza(ピザ)
bánh chocopie(チョコパイ)

これは「新しいものを取り入れて自文化で包む」というより、
初めて見る食べ物でも、その特徴から“bánhっぽい”と感じたらとりあえず bánh をつけてしまう
そんな実用的な感覚なのかもしれません。
「粉っぽい?」「丸い?」「蒸す?」「焼く?」
→ じゃあ bánh の仲間にしておこう、みたいな。
もちろん正確な理由はわかりませんが、ベトナム語の柔らかさのようなものを感じます。
5.共通点を探してみると…?
パンでも餅でもクレープでもお菓子でもある“bánh”。
共通点を見つけるのは簡単ではありませんが、あえてまとめるとすれば
「粉から作られた手頃なサイズの食べ物」
という点が近いように思います。

ただ、これはあくまで個人的な印象で、正確な分類ではありません。
ベトナムの人たちはもっと直感的に“bánhかどうか”を判断しているように見えます。
6.「Anh ăn bánh không?」――目の前に現物があれば bánh 単体で通じる
普段は曖昧な bánh ですが、
面白いのは 目の前に現物があると、単体で「食べる?」と使える ことです。
「Anh ăn bánh không?(アン・アン・バイン・コン?)」 =“これ食べる?”
こんな風に、bánh 単体で意味が通じます。
文脈と状況に頼る言語運用は、ベトナム語らしい柔らかさを感じる瞬間です。
7.“bánh なもの”というベトナム人の共通認識
ベトナム人に「bánhって何?」と聞いても、明確に定義する人は多くありません。
ですが「これは bánh?」と聞くと、ほとんどの人が即答します。
それは、はっきり線引きされた定義よりも
食文化の中で共有された“bánhらしさ” があるからかもしれません。

私自身も長年住んでいますが、
この“なんとなくの共通認識”のような文化的感覚が面白く、魅力に感じています。
8.考えれば考えるほどわからない。でもそれが心地よい
bánh を調べれば調べるほど定義は曖昧になります。
でも周囲のベトナム人はあまり気にしていないようで、「bánh は bánh だよ」と軽く笑うだけ。
そんな様子を見ると、
はっきり分類しなくても成り立つ曖昧さ、
そしてそれを自然に受け止めている文化の空気を感じることがあります。
あくまで日常生活の中で感じた印象にすぎません。
それでも、こうした曖昧さがベトナムの魅力の一つなのではないかという気がしています。