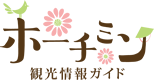目次
歴史を振り返ると、女性は常に重要な役割を担い、社会を築き上げる過程において欠かせない大きな力となってきました。どの時代、どの国、どの民族においても、女性は闘争や創造に関わり、その民族固有の伝統文化的価値を守り続ける上で中心的な存在でした。
今日では、社会生活のあらゆる分野において女性の役割がますます明確になり、国内外での地位を絶えず高めています。
1. 家庭における「火を守る人」から「働く母」へ
日常生活でよく見られるのは、早朝に子どもを送り届け、慌ただしくオフィスへ向かい、夜遅くに疲れた顔で帰宅してもなお、食事を作り、夫や子どもの世話を続ける母親たちの姿です。
彼女たちは決して不満を口にせず、家庭の温かさを守り続けています。
このことは、女性が単に「専業主婦」か「キャリアウーマン」のどちらかを選ぶのではなく、実際にはその両方を同時に担っていることを示しています。
まさにこの「二重の役割」は、負担であると同時に、現代女性の力強さや粘り強さ、そして不屈の精神を示す明確な証しでもあるのです。
🔹 ここでいう「火を守る人」とは、家庭の中で愛情・絆・幸福・温もりを絶えず維持する存在、すなわち家庭を守り続ける女性を指します。
🔹 一方で「創造する人」とは、社会に新しい価値を生み出す存在、すなわち職業上の活躍、事業経営、科学研究、芸術活動などを通じて、社会をより豊かに発展させる女性を意味します。
2. 経済と政治で光を放つ女性たち
開放経済の中で、ベトナム女性がどれほど力を発揮しているかは、身近なニュースでも日々感じます。ヴィナミルク社のマイ・キエウ・リエン氏、THグループのタイ・フオン氏といった名前は国際的にも知られていますが、私の周囲にも、小さなビジネスを立ち上げて家庭を支える女性が大勢います。
また、政治の場で女性議員が30%に達しているという事実は、数字以上に大きな意味を持ちます。私はそこに「声なき声」を代弁する力を感じ、誇りに思わずにはいられません。
3. 教育・科学・文化を支える女性
ベトナムの学校に行けば、先生の多くが女性であることに気づきます。私自身の恩師も女性が多く、その影響力は計り知れません。教育は次世代を形づくる根幹であり、そこで女性が果たす役割の大きさを考えると、社会の未来も彼女たちの手の中にあると感じます。
さらに、科学や文化の分野で活躍する女性の姿は「創造の力に性別はない」という事実をはっきりと示しています。
4. 日本女性との比較から見えること
ここで一度、日本女性と比較してみたいと思います。両国の女性には「仕事と家庭の両立」という共通の課題があります。ベトナムでも日本でも、「良妻賢母」という価値観が根強く残り、女性に二重のプレッシャーを与えています。
しかし違いもはっきりしています。日本では結婚や出産を機に多くの女性がキャリアを中断する傾向があります。いわゆる「M字カーブ」の現象です。対してベトナムでは、結婚後も働き続ける女性が多く、「仕事も家事もこなすマルチタスク型」が一般的です。これは良い意味でも悪い意味でも、ベトナムらしい特徴だと私は感じます。
また、政治参加の面では、ベトナム女性が日本を大きく上回っています。日本の伝統的な価値観や社会構造が女性の活躍を制約しているのに対し、ベトナムでは比較的開かれた環境があります。この差を見比べると、社会が女性に与えるチャンスの重要性を痛感します。
5. 機会と課題のはざまで
グローバル化の中で、ベトナム女性にはかつてないほど多くの機会が与えられています。知識や市場へのアクセス、国際的なキャリアの道。しかしそれは同時に「家庭も仕事も両方」という重圧をさらに強める側面もあります。
地方に行けば、今なお「男は外、女は内」という固定観念が残っている地域もありますし、都市部でも「キャリアも家庭も完璧に」という期待が女性を追い詰めています。私はここにこそ、これからの課題があると考えています。
結論 ― 私自身の視点から
ベトナム女性は、歴史のなかで常に時代を支える存在でした。そして現代においても、その姿は大きく変わりつつも本質は同じだと思います。つまり「家族を守り、社会を動かす力」こそが女性の強さなのです。
私は、日本社会と比較してみることで、ベトナム女性の粘り強さや柔軟さがいっそう際立っていると感じます。しかし同時に、課題も依然として存在し、女性が背負う二重の重圧は軽くなったとは言えません。
これからの時代に必要なのは、単に「女性が頑張る」ことではなく、社会全体が女性の可能性を支える仕組みを整えることだと考えます。家庭も社会も、女性が安心して能力を発揮できる環境を作ることで、ベトナムだけでなく世界全体がより豊かになるのではないでしょうか。
私自身、ベトナム女性の一人として、この歴史と現代の流れを誇りに思いながら、自分の力を社会にどう活かせるかを問い続けたいと思います。