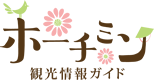現地の人を“怖い”と感じる日本人旅行者
ホーチミンの街を歩いていると、現地の人から話しかけられても無視して通り過ぎる日本人旅行者をよく見かけます。タクシーには乗らず、値札のない店では買い物を避け、声をかけられても構えたまま歩き続ける。
そんな行動の背景には、「現地の人は怖い」「騙されるかもしれない」という警戒心があるのだと思います。
ニュースやガイドブック、SNSで伝えられるのは、主にトラブルや被害の話。
“普通に安全に過ごせた”という体験は語られにくく、結果として悪い印象だけが記憶に残ります。
こうして、「アジア=危険」というイメージが強化されていくのです。

「警戒心」は生きるための本能
もちろん、警戒心を持つこと自体は悪いことではありません。
実際に旅行者を狙う人も存在しますし、海外では油断がトラブルを招くこともあります。
見知らぬ土地で自分を守るための慎重さは、旅人にとって大切な防衛本能です。
ただし、問題はその警戒が強すぎて“人との関わり”を遮断してしまうこと。
声をかけてきた人を全員疑いの目で見てしまえば、旅の中での温かい交流は生まれません。
ホーチミンのように人懐っこい街では、その距離感が旅の印象を大きく左右します。
自然体で接することの心地よさと、少しの羨ましさ
私自身は日常的にベトナム語で会話をしており、現地の人に対して特別な警戒心や、過剰にフレンドリーになろうとする意識はあまりありません。
道で声をかけられれば必要に応じて話し、必要がなければ軽く笑って通り過ぎる。
そんな“自然体の距離感”が自分にはしっくりきています。

一方で、旅行者の中には現地の人と積極的に話し、笑顔で交流している人もいます。
彼らは少し警戒心が低いのかもしれませんが、その分だけ純粋に人との出会いを楽しんでいるようにも見えます。
そんな姿を見かけると、「ああ、こういう旅の仕方も素敵だな」と羨ましく思うことがあります。
言葉が完全に通じなくても、心を開いて関わることでしか得られない瞬間が、きっとそこにあるのだと思います。
偏見のフィルターを外してみる
日本人の中には、ベトナムを含むアジアの国々を「まだ未発展で、貧しさが残る国」と見る意識が根強くあるのかもしれません。
そのため、「お金を持っている外国人は狙われるのではないか」と考える人が多いのも理解できます。

ただ、実際にベトナム人の友人に聞いてみると、15年ほど前は確かに現地の人でも「ひったくりやぼったくりに気をつけたほうがいい」と言われていたそうです。
しかし今では、そうした心配をすることはほとんどなくなったといいます。
街の安全性は年々高まり、昔のような混沌とした時代ではなくなっています。
それでも、私たちの中に残る古いイメージが、無意識のうちに現地の人を警戒させていることもあります。
実際に生活してみると、多くのベトナム人は親切で誠実で、いたって普通に働いています。
彼らを“危険な存在”と一括りにしてしまうのは、人間らしい温かさを感じる機会を自ら狭めてしまうようなものです。
自分の中の警戒心を見つめる
海外旅行で「誰が安全で、誰が危険か」を見極めるのは、実際とても難しいことです。
だからこそ、相手を見定めようとするよりも、自分自身の警戒心と向き合うことが大切だと思います。
「自分は今、相手を必要以上に疑っていないだろうか?」
そう問いかけてみるだけで、見える世界が少し変わるかもしれません。

旅先での安全と、人との出会いは両立します。
警戒しすぎず、無防備すぎず、ほんの少しだけ心を開いてみる。
そのわずかな勇気が、旅の中でのかけがえのない瞬間を運んできてくれるんじゃないかな〜と考えています。